 中国史
中国史 三十六計とは?その概要と現代における応用
三十六計は、中国の古代兵法書『三十六計』に基づく戦略や戦術を表現する言葉です。歴史的には戦争の際に使用されることが多かったこれらの計略は、現代においてもビジネスや人間関係における戦術として活用されています。本記事では、三十六計の基本的な意味...
 中国史
中国史  日本史
日本史 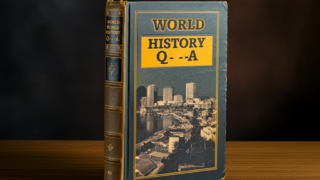 世界史
世界史  全般
全般  中国史
中国史  日本史
日本史 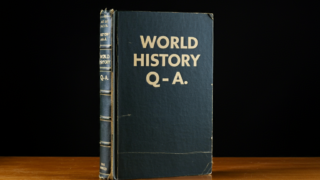 世界史
世界史  全般
全般  中国史
中国史  日本史
日本史