 世界史
世界史 ボリシェビキの成功の理由とその支持層:ソ連成立の背景
1910年代から1920年代にかけて、ボリシェビキ率いるソ連は多くの内外の困難を乗り越え、最終的にソ連の基盤を築きました。大戦による国土の荒廃、白軍や外国勢力の侵入、内部の社会的対立など、多くの挑戦があった中で、なぜボリシェビキはその後の困...
 世界史
世界史  全般
全般  中国史
中国史  日本史
日本史 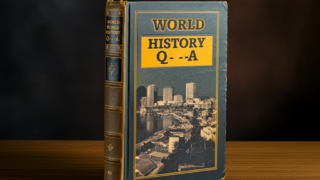 世界史
世界史  中国史
中国史  日本史
日本史 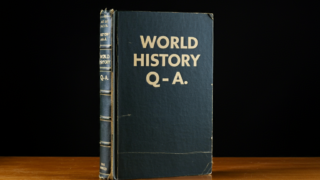 世界史
世界史 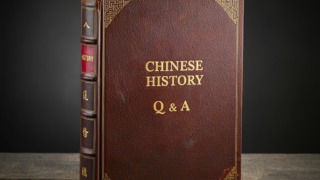 中国史
中国史  日本史
日本史