 全般
全般 旭日旗の意味と歴史: その背景と用途について詳しく解説
旭日旗は、日本の歴史的・文化的な象徴の一つであり、現在でも様々な場面で使用されています。特にそのデザインや意味については誤解を招くこともあります。本記事では、旭日旗の起源やその歴史、現代における用途について詳しく解説します。旭日旗とは?旭日...
 全般
全般  中国史
中国史  日本史
日本史 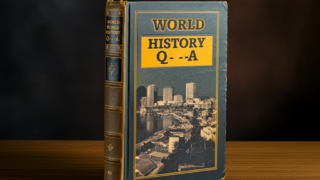 世界史
世界史 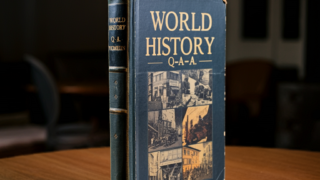 全般
全般 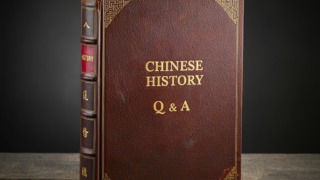 中国史
中国史  日本史
日本史  世界史
世界史  全般
全般  中国史
中国史