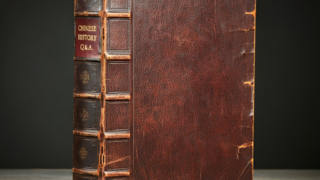 中国史
中国史 中国唐王朝の皇位継承: 長孫無忌の死後の可能性について
中国唐王朝の皇位継承についての歴史的な疑問は、非常に興味深いものです。特に、長孫無忌がもし早く死んでいた場合、房玄齢がより長生きし、三男である呉王李恪が三代目皇帝になっていた可能性については、歴史の分岐点を考える上で重要なテーマです。本記事...
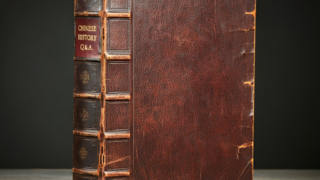 中国史
中国史 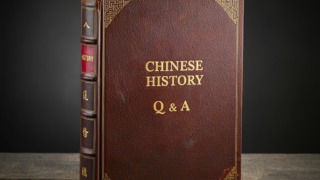 中国史
中国史  中国史
中国史  中国史
中国史  中国史
中国史  中国史
中国史  中国史
中国史  中国史
中国史  中国史
中国史  中国史
中国史