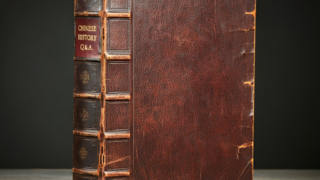 中国史
中国史 三国志時代の城とその構造:擁壁と天守閣の違いについて
三国志時代の城の構造についてよく見かけるのは、高い外周の擁壁です。このような城のイメージは、映画やドラマでも多く取り上げられており、非常に印象的です。しかし、日本の城と違って、三国志時代の中国の城においては、天守閣のような高い建物が存在した...
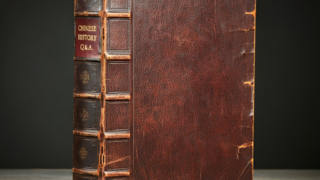 中国史
中国史  中国史
中国史 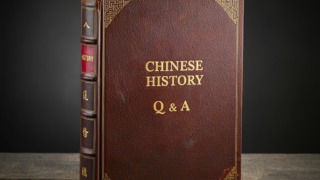 中国史
中国史  中国史
中国史  中国史
中国史  中国史
中国史  中国史
中国史  中国史
中国史  中国史
中国史  中国史
中国史