 中国史
中国史 中国の内戦もし蒋介石側が勝利していた場合の影響:アメリカとの関係とその後の展開
中国の内戦(国共内戦)は20世紀の最も重要な歴史的出来事の一つであり、もし蒋介石側の国民党が勝利していた場合、現代の中国の政治や国際関係はどのように変わったのでしょうか?特に、アメリカとの関係について考察すると、蒋介石側が勝っていた場合、中...
 中国史
中国史  中国史
中国史 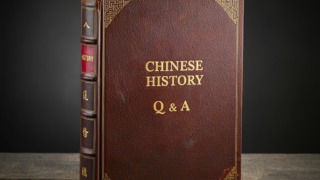 中国史
中国史  中国史
中国史  中国史
中国史  中国史
中国史  中国史
中国史 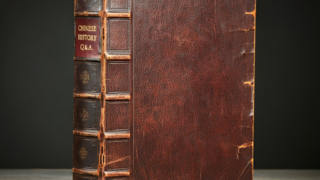 中国史
中国史  中国史
中国史  中国史
中国史