 中国史
中国史 毛沢東と儒教:文化大革命と古典文学の矛盾
毛沢東の文化大革命における儒教否定と、彼が実際に古典文学を愛読していたという事実には確かに矛盾が見受けられます。毛沢東は文化大革命の中で「批林批孔運動」を通じて儒教や古典的な教養を徹底的に否定しましたが、同時に彼自身が古典文学を重視し、愛読...
 中国史
中国史 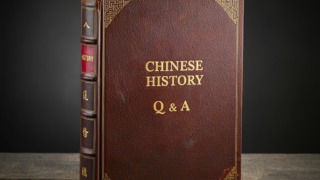 中国史
中国史  中国史
中国史  中国史
中国史 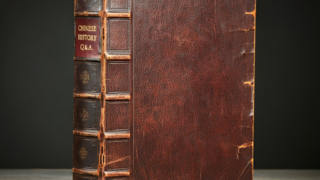 中国史
中国史 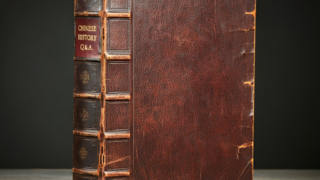 中国史
中国史 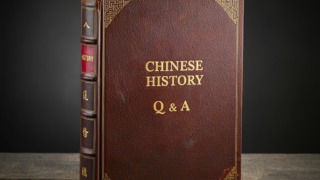 中国史
中国史 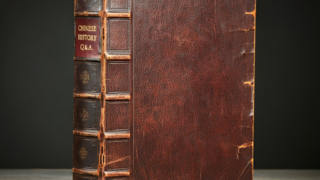 中国史
中国史 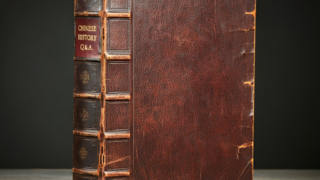 中国史
中国史 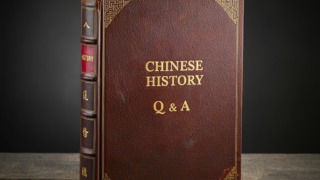 中国史
中国史