 中国史
中国史 後漢・三国時代の交通手形とは?発行者、形状、内容、発行目的を解説
後漢末から三国時代にかけて、中国では交通手形(途行手形)が重要な役割を果たしていました。これらの手形は、軍事・行政・商業活動において、通行の許可や物資の輸送を円滑にするために使用されました。交通手形の発行者とその目的交通手形は、主に地方の太...
 中国史
中国史 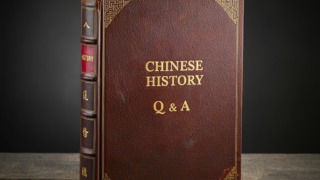 中国史
中国史  中国史
中国史 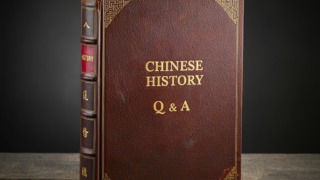 中国史
中国史  中国史
中国史 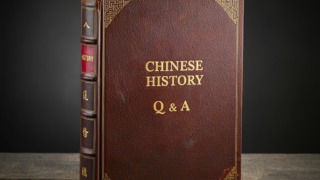 中国史
中国史  中国史
中国史  中国史
中国史  中国史
中国史 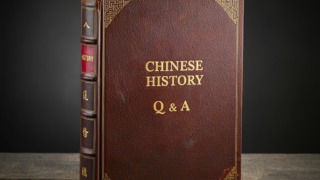 中国史
中国史