 全般
全般 戦没者の調べ方: 戦死した祖父の艦や情報を探す方法
戦没者の調査は、祖父がどの艦に乗っていたのか、戦争でどのような経緯で亡くなったのかを知るために非常に重要な作業です。この記事では、戦没者を調べる方法や情報を見つける手段について紹介します。戦没者の情報を調べるための基本的な方法戦没者を調べる...
 全般
全般 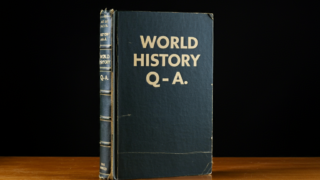 全般
全般  全般
全般  全般
全般  全般
全般  全般
全般  全般
全般  全般
全般  全般
全般 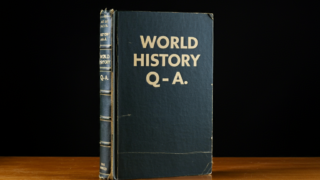 全般
全般