 中国史
中国史 華県地震と明王朝の時代背景
華県地震は、明王朝時代に発生した大規模な自然災害として広く知られています。明王朝は、14世紀から17世紀にかけて中国を支配していた王朝で、その治世の中で多くの歴史的事件が発生しました。今回は、華県地震が発生した当時の明王朝の状況を詳しく解説...
 中国史
中国史  日本史
日本史  世界史
世界史  全般
全般 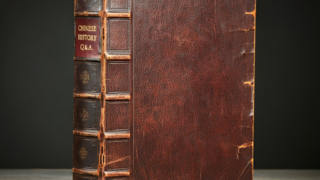 中国史
中国史  日本史
日本史 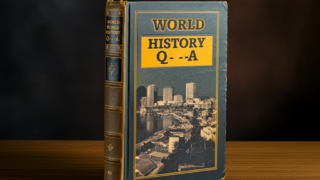 世界史
世界史  中国史
中国史  日本史
日本史 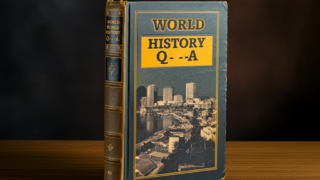 世界史
世界史