 世界史
世界史 社会主義経済の改革とその限界: 「社会主義の範囲内で」の枠組みとは
社会主義国が経済を立て直そうと試みた場合、しばしば「社会主義の範囲内で」という制約の中で行われる改革が中途半端に終わることが指摘されています。これは、社会主義の理念と実際の経済的な要求との間に大きなギャップが存在するためです。この記事では、...
 世界史
世界史  全般
全般  中国史
中国史  日本史
日本史  世界史
世界史  全般
全般  中国史
中国史  日本史
日本史 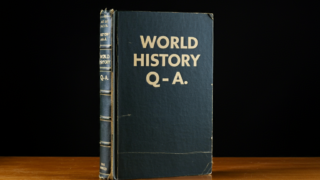 世界史
世界史  中国史
中国史