 日本史
日本史 太平洋戦争における日本の南進論と北進論:南進論選択の決定的な要因
太平洋戦争中、日本は南進論と北進論という二つの戦略的選択肢の間で議論していました。最終的に選ばれたのは南進論であり、この選択が戦局に与えた影響は計り知れません。本記事では、なぜ日本が南進論を選択したのか、その背景にある政治的、経済的、そして...
 日本史
日本史  世界史
世界史  中国史
中国史  日本史
日本史 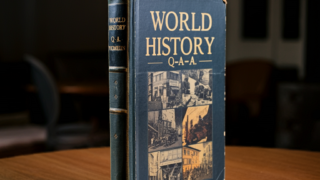 世界史
世界史 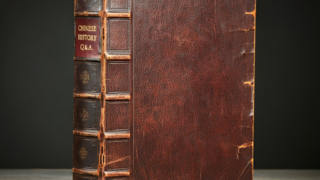 中国史
中国史  日本史
日本史  世界史
世界史  中国史
中国史  日本史
日本史